7つの習慣の原則一覧と成功の地図【完全ガイド】

こんにちは!スルースのVictory Academy、運営者の「スルース」です。
「7つの習慣」って有名ですけど、いざ「原則一覧」を探してみると、情報が多くて混乱してしまうこと、ありますよね。
私的成功とか公的成功とか、言葉は知っていても、結局のところ「原則」って何?「習慣」とどう違うの?と疑問に思うかもしれません。
パラダイムシフトなんて言葉も出てきますし、全体像を掴むのが少し難しいかも、と感じる方もいるでしょう。
また、7つの習慣の基礎原則や、第1の習慣から第7の習慣までの流れを、わかりやすく要約して知りたい、という方も多いかなと思います。結局、どの順番で何をすればいいのか、そのロードマップが欲しいですよね!
この記事では、そんな「7つの習慣の原則一覧」について、その核となる考え方から各習慣のポイントまで、できるだけシンプルに、そして本質を掴めるように私なりに噛み砕いてまとめてみました。
成功へのロードマップとして、ぜひ参考にしてみてくださいね!
記事のポイント
- 7つの習慣の「原則」と「習慣」の根本的な違い
- すべての土台となる「3つの基礎原則」とは何か
- 依存から自立へ至る「私的成功」の原則一覧
- 自立から相互依存へ至る「公的成功」の原則一覧
本記事は一般的な情報提供を目的としており、成果を保証するものではありません。健康・メンタルや法務・財務等に関する個別のご相談は、必要に応じて専門家へご相談ください。
7つの習慣の原則一覧と基礎原則
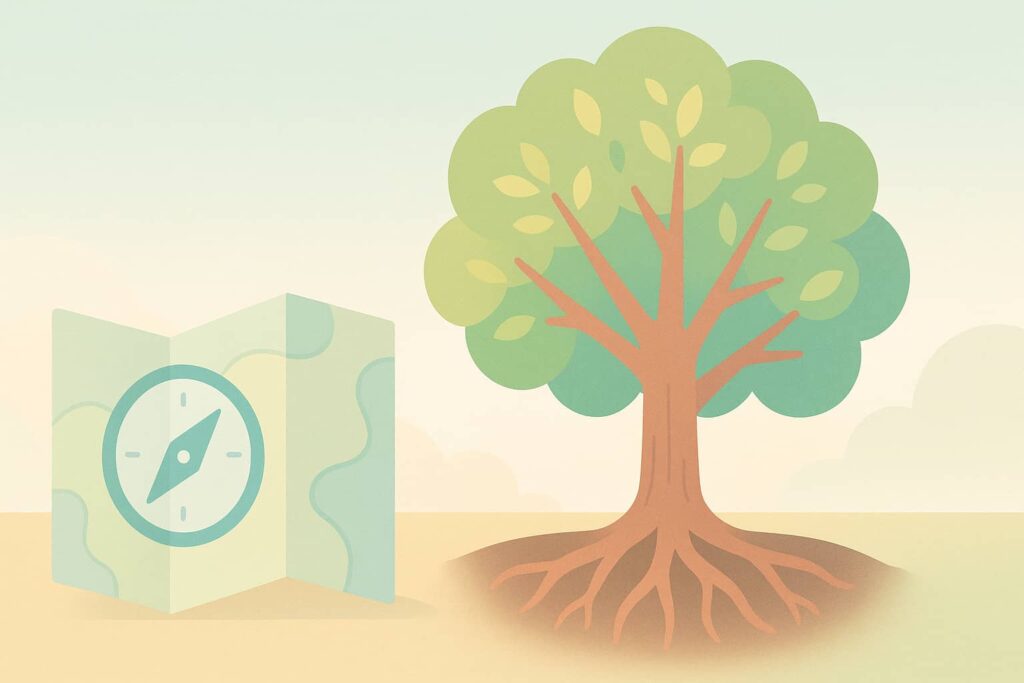
『7つの習慣』の旅へようこそ!まずは、この哲学の根幹を成す「原則」とは一体何なのか、そしてすべての習慣を実践する前に理解しておくべき「基礎原則」について、じっくりと見ていきましょう。ここが一番のキモであり、スタート地点です!
7つの習慣の「原則」とは?

「7つの習慣」っていうと、どうしても具体的な7つの行動(習慣)そのものに目が行きがちですよね。
でも、著者であるスティーブン・R・コヴィー博士が本当に伝えたかったのは、そのもっと奥深く、すべてを支える土台となる「原則(Principles)」の重要性なんです。
博士は、近年の成功に関する考え方が、表面的なものに偏っていると指摘しています。
彼は成功へのアプローチを2つに分類しました。
- 個性主義(Personality Ethic): 見た目や話し方、対人関係のテクニック、ポジティブ・シンキングといった「表面的なスキル」に焦点を当てる考え方です。これは木の「幹・枝・葉」に例えられます。
- 人格主義(Character Ethic): 誠意、謙虚、忍耐、公正、正義といった「人間の内面にある人格の核」に焦点を当てる考え方です。こちらは木の「根っこ」に例えられます。
どれだけ立派な枝葉(個性主義のテクニック)を持っていても、それを支える根っこ(人格主義)が浅ければ、ちょっとした嵐(人生の困難)ですぐに倒れてしまいますよね。
『7つの習慣』でいう「原則」とは、この「人格主義」の核を成す、普遍的で不変の法則のことを指します。
「公正さ」「誠実さ」「忍耐」「奉仕」といった、時代や国、文化を超えて私たちの良心に根付いている価値観です。
これらは、自然界における「重力」のようなもので、私たちが知っていても知らなくても、私たちの長期的な結果に必ず影響を与えます。これが成功への「羅針盤」になるわけです。
「原則」と「習慣」の関係性
- 原則 = 成功のための普遍的な法則(人格・根っこ・羅針盤)
- 習慣 = 原則を実践するための具体的な行動体系(スキル・枝葉・航海術)
つまり、「7つの習慣」とは、この「原則」という羅針盤(目的地)に自分自身を合致させ、そこへ向かうための具体的な「航海術」を体系化したもの、ということですね!
押さえるべき3つの基礎原則

7つの習慣という「航海術」を学ぶ前に、まず私たちの「現在地」と「考え方の土台」を整える必要があります。
それが、次の3つの「基礎原則」です。
これが分かっていないと、習慣を実践しても効果が出にくいかもしれません。
1. パラダイムとパラダイムシフト
「パラダイム」って聞くと、ちょっと難しく感じますよね。でも、要は「ものの見方」や「捉え方」のことです。コヴィー博士はこれを「地図」に例えています。
もしあなたが東京に行きたいのに、大阪の地図(パラダイム)を持っていたらどうでしょう?
どれだけ一生懸命努力して(行動)、どれだけポジティブに考えても(態度)、目的地には絶対にたどり着けませんよね。
例えば、「仕事がうまくいかないのは、全部あの上司のせいだ」という地図(パラダイム)を持っている限り、いくら行動(残業する、資格を取る)を変えても、根本的な状況は好転しにくいかもしれません。
「パラダイムシフト」っていうのは、この「地図」そのもの(ものの見方)を根本的に変えることです。
結果を変えたいなら、行動や態度を小手先で変える前に、まず「見方(地図)」を変えよう、というのが最初の一歩です。
2. インサイド・アウト
これが『7つの習慣』の哲学の中で、最も中核をなす概念だと私は思います。
すべての変化は、自分の「内側」から「外側」へ(Inside-Out)というアプローチです。
問題が起きた時、私たちはつい原因を「外側」(他人、環境、経済状況)に求めてしまいがちです。「あいつが悪い」「会社が悪い」と。これを「アウトサイド・イン」のアプローチと呼びます。
でも、コヴィー博士は「問題が自分の外にあると考えるならば、その考え方こそが問題である」と断言しています。
なぜなら、私たちが本当にコントロールできるのは、自分の内側(パラダイム、人格、動機)だけだからです。
「インサイド・アウト」とは、まず自分自身の内面を変革することから始め、その結果として外側の状況を好転させていくという、自責的なアプローチなんですね。
インサイド・アウト vs アウトサイド・イン
- インサイド・アウト(自責): 自分の内面(パラダイム、人格)から変革を始める。
- アウトサイド・イン(他責): 自分の不幸を外部環境(他人、状況)のせいにする。
他人を変えようとするのは凄く難しいですが、自分を変えることは(難しくても)可能ですからね!
3. 人格主義
これは冒頭でも触れましたが、インサイド・アウトのアプローチによって変革すべき「内面」とは、具体的に何か? それこそが「人格(Character)」です。
『7つの習慣』は、本当の成功を目指すなら、まず成功を支える土台となる人格(誠実さ、謙虚さ、忍耐、公正さなど)を構築することが、何よりも重要であると説いています。
これら3つの基礎原則は、「アウトサイド・イン(他責)」というパラダイムを捨て、「インサイド・アウト(自責)」へと『パラダイムシフト』し、自分自身の『人格』を磨き始めること、という一連のプロセスを示しています。これが、第1の習慣を学ぶ前に必要な絶対的条件となるわけです!
成長の順番:依存から自立へ

7つの習慣は、ランダムなテクニックの寄せ集めではありません。そこには人間の「成長プロセス」に沿った、非常に論理的な順番があります。
これを「成長の連続体(Maturity Continuum)」と呼びます。
私たちは皆、次のようなステップで成長していきます。
- 依存(Dependence): 生まれたばかりの赤ん坊のように、他者の助けなしでは生きられない状態。精神的には「あなたのせいだ」「あなたがやってくれない」と、他者に頼り、他者の言動によって自分の感情や行動が左右される状態です。(主語が「あなた」)
- 自立(Independence): 自分の力で考え、行動し、その結果に責任を持つことができる状態。「私はできる」「私が選択する」というマインドです。(主語が「私」)
- 相互依存(Interdependence): 「自立」した個人同士が、お互いの強みを活かして協力し、一人では成し遂げられない、より大きな成果を生み出す状態です。「私たちがやろう」というマインドです。(主語が「私たち」)
7つの習慣の構成は、この3つの成長ステップを達成するために、明確な順番で構成されています。
- 私的成功(Private Victory): 第1~第3の習慣「依存」の状態から脱却し、「自立」した個人になるための土台を築く領域です。自分自身を律する力を身につけます。
- 公的成功(Public Victory): 第4~第6の習慣「自立」した個人として、「相互依存」の関係性を築く領域です。他者と効果的に関わり、協力してより大きな成果を生み出します。
- 再新再生(Renewal): 第7の習慣は、上記すべて(第1〜第6)を継続的に向上させるための習慣です。
この「順番」が非常に重要です。コヴィー博士は、「私的成功」という自立の土台がなければ、他者と効果的な関係を築く「公的成功」は絶対に望めないと強調しています。
考えてみれば当然かもですが、他責で依存的な人(「あなたのせいだ」と思っている人)同士が集まっても、真の協力関係(相互依存)なんて築けませんよね。まず「私」を確立することが、すべてのスタートなんです!
私的成功(第1~第3の習慣)を要約
ここからは、いよいよ具体的な習慣に入っていきます。まずは「私的成功」、つまり「依存」状態から抜け出して「自立」した個人になるための3つの習慣です。これは自分自身を律し、マネジメントする領域ですね。
第1の習慣:主体的である

第1の習慣「主体的である」は、他のすべての習慣の基礎となる、最も重要な習慣です。
これを一言で言えば、「自分の人生の責任は、100%自分で引き受ける」ということです。
私たちは日々、様々な「刺激(Stimulus)」(例:上司から理不尽に注意を受ける、満員電車で押される)を受けます。
多くの人は、この刺激に対して感情的に「反応(Response)」してしまいます(例:カッとなって言い返す、イライラする)。
しかし、主体的な人は、刺激と反応の間に「スペース(選択の自由)」を持つことを知っています。このスペースの中で、私たちは自分の反応を「選択」できるんです。
人間特有の4つの能力
この「反応を選択する力」は、動物にはない、人間特有の4つの能力によって可能になります。
- 自覚: 自分自身を客観的に見る能力。
- 想像力: 現実以外の可能性(もしこうしたら?)を考える能力。
- 良心: 善悪を判断し、心の奥にある原則を感じ取る能力。
- 意志: 周囲の状況に関わらず、自らの選択を実行する能力。
主体的な人は、これらの力を行使して、発する言葉を変えます(例:「~のせいだ」ではなく「私に何ができるか」)、そして自ら責任を取るんですね。
「影響の輪」への集中
この習慣を実践する上でカギとなるのが、「影響の輪(Circle of Influence)」という考え方です。
関心の輪 vs 影響の輪
- 関心の輪: 自分が関心あること全体(天候、経済、他人の欠点、政治など)。
- 影響の輪: その中で、自分がコントロール可能(影響を及ぼせる)な事柄(自分の言動、学習、態度、健康管理など)。
反応的な人は、コントロールできない「関心の輪」に意識を集中させ、不平や不満を口にします。結果、エネルギーを浪費し、影響の輪はどんどん小さくなります。
主体的な人は、コントロールできる*「影響の輪」に意識を集中させます*。他人を変えようとするのではなく、まず自分が変わる(学習する、態度を改める)ことで、周囲に良い影響を与えようとします。結果、影響の輪はどんどん広がっていきます。
第2の習慣:終わりを思い描く

第1の習慣で「自分の人生の運転席」に座ったら、次にするのは「行き先を決める」ことです。
それが第2の習慣「自分にとって本当に大切なこと(人生のゴール)を明確にしてから、今日一日を始めよう」という習慣です。
コヴィー博士は、この習慣を理解するために「自分自身の葬儀の場面を想像してみてください」という強烈なワークを提案しています。
参列者(家族、友人、同僚)に、自分の人生をどう語ってほしいか? そこから逆算して、「本当に大切にしたい価値観」を見つけるんです。
すべてのものは二度創造される
この習慣の背景には、「すべての物事は、二度創造される」という原則があります。
- 第1の創造(知的創造): 頭の中での計画や設計図。(例:家を建てる前の設計図)
- 第2の創造(物的創造): 実際の行動や実行。(例:設計図に基づく建設)
問題は、この「第1の創造(設計図)」を、他人や環境、あるいは過去の習慣に流されるままに描いていないか?ということです。
第2の習慣は、この「第1の創造」を、自分自身で主体的に行うことを意味します。
ミッション・ステートメントの作成
第1の創造を具体的な形にするのが、「ミッション・ステートメント(個人の憲法)」の作成です。これは、自分の理念や信条を文章化したものであり、人生におけるあらゆる行動や決断の「判断基準(羅針盤)」となります。
ミッション・ステートメントは、「自分はどんな人間になりたいのか(人格)」「何をしたいのか、何を成し遂げたいのか(貢献、功績)」「自分はどんなことを大事にしているのか(価値観)」といった要素を深く掘り下げて作成します。
これがなければ、僕たちは日々の忙しさに流され、「緊急だが重要でないこと」に振り回される人生を送ってしまうかもしれませんね。
第3の習慣:最優先事項を優先する

第1の習慣(主体性)で運転席に座り、第2の習慣(目的)で羅針盤(ミッション)を手に入れたら、いよいよ「実行」です。
第3の習慣は、第2の習慣(知的創造)で定めたミッションに基づき、「最優先事項(本当に価値のあること)」を日々実践(物的創造)する習慣です。
これは単なる時間管理(Time Management)ではなく、第1と第2の習慣に基づいた「自己管理(Self-Management)」の習慣です。
時間管理のマトリックス
この習慣を実践する上で非常に有名なツールが、「時間管理のマトリックス」です。
すべての活動を「緊急度」と「重要度」の2つの軸で4つの領域に分類します。
| 重要(Important) | 重要でない(Not Important) | |
|---|---|---|
| 緊急(Urgent) | 第I領域(必須の領域) ・危機、災害、病気 ・クレーム対応 ・締め切りのある仕事 | 第III領域(錯覚の領域) ・無意味な電話、メール ・多くの会議 ・突然の来客 |
| 緊急でない(Not Urgent) | 第II領域(効果性の領域) ・人間関係づくり ・準備、計画、予防 ・健康維持、自己啓発 ・(第7の習慣:刃を研ぐ) | 第IV領域(浪費・過剰の領域) ・暇つぶし ・だらだら見るテレビ ・多くのネットサーフィン |
多くの人は、「緊急なこと」(第I領域と第III領域)に追われる生活を送っています。
特に第III領域は、緊急に見えるだけで実は重要ではない「錯覚の領域」であり、注意が必要です。
しかし、本当に効果的な人生を送る人は、「重要だが緊急でない」第II領域に意図的に時間を投資します。
第II領域(準備、計画、予防、人間関係構築、自己研鑽)に注力することで、将来発生するであろう第I領域(危機、クレーム)を未然に防ぎ、減らすことができるんです。
これがまさに「自己管理」です。
この習慣は、重要でない活動(第III、第IV領域)に「ノー」と言い、最も重要な第II領域を最優先する自己管理能力を問うものです。
私的成功(第1〜3の習慣)は、
- 自分が創造主であると「自覚」し(第1)
- 人生の設計図を「知的創造」し(第2)
- 設計図に基づいて日々「物的創造」を実行する(第3)
という一連のプロセスによって達成されます。
7つの習慣の原則一覧【公的成功】

さて、「私的成功」(第1~3の習慣)によって「依存」から「自立」した個人になれたら、次のステージは「公的成功」です。
「私」を確立した私たちが、どうやって他者と関わり、「私たち」としてより大きな成果を生み出すか。ここでは、そのための「相互依存」の原則を見ていきましょう!
公的成功(第4~6の習慣)を要約
第4から第6の習慣は「公的成功」、つまり「相互依存」の関係性を築くための領域です。繰り返しになりますが、これは「私的成功(自立)」という土台が絶対的に必要です。自分を律することができて初めて、他者と効果的な関係を築けるんです!
第4の習慣:Win-Winを考える

これは、人生を「競争の場(一方が勝てば他方が負ける)」としてではなく、「協力の場」として捉えるマインドセットです。問題や課題に直面した際、**自分も勝ち、相手も勝つ(双方が満足する)**方法を常に探求する姿勢を指します。
「豊かさマインド」vs「欠乏マインド」
Win-Winの考え方は、「豊かさマインド(Abundance Mentality)」に基づいています。
これは、世の中の成功、幸福、利益は、全員に行き渡るほど十分に存在する(パイは無限にある)というパラダイムです。
対照的に、Win-Lose(自分が勝ち、相手が負ける)の考え方は、「欠乏マインド(Scarcity Mentality)」に基づいています。
パイは限られており、他人が取れば自分の分が減る、という奪い合いのパラダイムですね。
「勇気」と「思いやり」のバランス
Win-Winの実現には、2つの側面が高いレベルでバランスしている必要があります。
- 勇気: 自分の考えや思いを相手にしっかりと伝える意欲と能力。
- 思いやり: 相手を尊重し、相手の考えや思いを求めて聴く意欲と能力。
「勇気」だけが高ければWin-Lose(自分の勝ち)に、「思いやり」だけが高ければLose-Win(自分の負け)に陥ってしまいます。両方を高いレベルで保つことが、Win-Winの鍵です!
人間関係の6つのパラダイム
Win-Winの価値は、他の人間関係のパラダイムと比較することで明確になります。
| パラダイム | 定義と特徴 |
| 1. Win-Win | 自分も勝ち、相手も勝つ。双方が満足し、長期的な信頼関係を築く。 |
| 2. Win-Lose | 自分が勝ち、相手が負ける。競争や比較のパラダイム。 |
| 3. Lose-Win | 自分が負け、相手が勝つ。自己犠牲や服従のパラダイム。 |
| 4. Lose-Lose | 自分も負け、相手も負ける。Win-Lose同士が衝突した結果など。 |
| 5. Win | 自分だけが勝つことしか考えない。相手のWin/Loseは考慮しない。 |
| 6. Win-Win or No Deal | Win-Winの関係が構築できない場合は、「取引しない(No Deal)」という選択肢を持つ。これにより、Win-LoseやLose-Winの関係を強制的に結ぶことを避ける。 |
特に「Win-Win or No Deal(取引しない)」という選択肢を持つことは、健全な関係性を築く上で非常に重要です!
第5の習慣:まず理解に徹し、そして理解される

これは、公的成功における、コミュニケーションの最も重要な原則だと思います。
私たちは通常、まず「自分を理解してもらおう」(自分の意見を先に主張しよう)としがちです。
この習慣は、その順序を根本から逆転させます。まず相手を心から理解することに全力を尽くす。そのあとで初めて、自分を理解してもらう、という順番です。
共感による傾聴(Empathetic Listening)
相手を真に理解するためのスキルが「共感による傾聴」です。
これは、コヴィー博士が提唱する「聞く」レベルの最高段階(レベル5)です。
単に言葉を聞く(レベル3:選択的に聞く、レベル4:注意して聞く)のではなく、相手の立場に立ち、相手のパラダイム(ものの見方)に入り込み、相手の感情や意図を理解しようという「意図」を持って聴く聴き方です。
これは、相手との信頼関係(信頼口座)への最大の預け入れとなります。
回避すべき「自叙伝的反応」
私たちが相手の話を聞く際、無意識に自分の経験(自叙伝)に基づいて反応してしまいがちです。
これが相手の真の理解を妨げる最大の罠です。避けるべき4つの「自叙伝的反応」は以下の通りです。
理解を妨げる4つの「自叙伝的反応」
- 評価する: 相手の話に「同意する」または「反対する」。(例:「その考えは甘いよ」「私もそう思う」)
- 探る: 自分の視点や好奇心から質問する。(例:「それで、結局何があったの?」「彼はなんて言ったの?」)
- 助言する: 自分の経験から解決策を提示する。(例:「私ならこうするね」「サウナに行けばいいよ」)
- 解釈する: 自分の動機や理論で相手の心理を分析する。(例:「それは要するに、君が認められたいってことだろ」)
相手が求めているのは(多くの場合)診断や助言ではなく、まず「共感」です。これらの反応をグッと止め、相手が心を開くまで「共感による傾聴」に徹することが、第5の習慣の実践なんですね!
第6の習慣:シナジーを創り出す

第6の習慣「シナジーを創り出す」は、公的成功(相互依存)の最終段階であり、最高潮です。
シナジー(相乗効果)とは、全体の総和が個々の部分の合計よりも大きくなる状態、すなわち 1+1=3(あるいはそれ以上)となる状態を指します。
一人では決して成し得ない卓越した成果を、他者との協力によって達成することです。
「違い」を尊重し、活用する
シナジーは「妥協(Compromise)」とは全く異なります。妥協は、お互いが少しずつ譲歩し、結局どちらも不満が残る状態(1+1=1.5)になりがちです。
シナジーの前提は、お互いの「違い」を尊重することです。
自分と異なる意見やパラダイム(ものの見方)を、脅威や対立の種としてではなく、新たな可能性を生み出す貴重な資源として歓迎する姿勢が求められます。
「第3の案」の探求
シナジーは、「私の案(Win-Lose)」でも「あなたの案(Lose-Win)」でも「妥協案」でもない、両者の案を超えた、これまで存在しなかった「第3の案(3rd Alternative)」を創造するプロセスです。
これは、第1の習慣(主体性)を持ち、第4の習慣(Win-Winの精神)で向き合い、第5の習慣(共感による傾聴のスキル)でお互いを深く理解し合う…という、これまでの習慣すべてを総動員することによってのみ達成可能な、創造的協力なんですね。
第7の習慣:刃を研ぐ

最後の第7の習慣は、これまでの第1~第6の習慣すべてを支えるための「メンテナンス」の習慣です。
コヴィー博士は、木を切るきこりの話に例えています。
ノコギリを使い続ければ、刃は鈍り、やがて切れなくなります。効率的に木を切り続けるためには、一度手を止め、「刃を研ぐ」時間が必要です。
第7の習慣は、他の6つの習慣すべてを実践するための「自分自身」という最も重要な資源(ノコギリの刃)を、継続的にメンテナンスし、再新再生(リニューアル)する習慣です。
この習慣は、他の6つの習慣を実践するための能力とエネルギーを維持する土台となります!
「4つの側面」のバランスよい再生
刃を研ぐとは、単に休むことではありません。コヴィー博士は、人間を構成する「4つの側面」すべてにおいて、バランスよく刃を研ぐことが重要であると説いています。
自分を研ぐ「4つの側面」
- 肉体的側面: 体に良い食事、十分な睡眠・休養、定期的な運動。日々の活動エネルギーを生み出す、資本となる身体のメンテナンスです。
- 精神的側面: 自分の価値観を明確にし、向き合う時間。瞑想、音楽鑑賞、自然に触れる、読書(特に古典など)、日記などを通じて内面を成長させ、第2の習慣(ミッション)と繋がります。
- 知的側面: 知識を増やし、思考力を高めること。新しいスキルの学習、良質な読書、計画、文章を書くことなどにより、知的生産性を高めます。
- 社会・情緒的側面: 他者との良好な関係性を育むこと。家族や友人との交流、他者への共感(第5の習慣の実践)、奉仕活動など。公的成功(第4~6の習慣)と深く関わります。
これらの4つの側面は、どれか一つでも疎かにすると、全体のバランスが崩れてしまいます。
成長のらせん(Upward Spiral)
第7の習慣(刃を研ぐ)を実践することで、自分自身の能力が高まり、第1〜第6の習慣を、前回よりも高いレベルで実践できるようになります。
この継続的な改善のプロセスを「成長のらせん(Upward Spiral)」と呼びます。
そして、お気づきの方もいるかもですが、この「刃を研ぐ」活動は、まさに第3の習慣で定義された「第II領域(重要だが緊急でない)」の活動そのものなんですね。
つまり、第3の習慣で学んだ「最優先事項(第II領域)」に時間を投資し、第7の習慣で「具体的に4つの側面を研ぐ」。
この実践が、第1の習慣である「主体的である」ためのエネルギーを生み出し、システム全体がループし、らせん状に成長していくのです。
まとめ|7つの習慣の原則一覧
今回は、7つの習慣の原則一覧について、その土台となる考え方から、私的成功(依存→自立)、公的成功(自立→相互依存)、そして自己再生(刃を研ぐ)のプロセスまでを、できるだけ詳しくまとめてみました。
『7つの習慣』は、読めば読むほど新しい発見がある、本当に奥深い本です。単なるテクニック集ではなく、「インサイド・アウト」のアプローチで自分自身の「人格(原則)」を磨き続ける、一生ものの哲学だなと改めて感じます。
もちろん、これらすべてを一度に実践するのは難しいかもしれません。
コヴィー博士も、まずは「私的成功」、特に「第1の習慣:主体的である」から始めることを推奨しています。
まずは自分の「影響の輪」に集中し、自分の反応を選択することから、少しずつでも日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたの成功へのロードマップ作りの、そしてより良い人生を歩むための「羅針盤」を見つける参考になれば幸いです。
参考文献(原典・公式):
・Covey, Stephen R. The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary Edition. Simon & Schuster, 2020.
ISBN: 978-1982137137
https://www.simonandschuster.com/books/The-7-Habits-of-Highly-Effective-People/Stephen-R-Covey/9781982137137
・スティーブン・R・コヴィー(著)/フランクリン・コヴィー・ジャパン(訳)
『完訳 7つの習慣—人格主義の回復』 キングベアー出版(FCE)
公式ページ(出版社):https://fce-publishing.co.jp/book/p863940246/
・スティーブン・R・コヴィー(著)/フランクリン・コヴィー・ジャパン(訳)
『完訳 7つの習慣—30周年記念版』 キングベアー出版(FCE), 2020.
ISBN: 978-4863941014
公式ページ(出版社):https://fce-publishing.co.jp/book/p863941013/
・FranklinCovey(公式)The 7 Habits 書籍・解説ページ(英語)
書籍紹介(公式):https://www.franklincovey.com/books/the-7-habits-of-highly-effective-people/
コース概要(補足):https://www.franklincovey.com/courses/the-7-habits/





