はじめに
「やらなきゃいけないのに、どうしてもやる気が出ない…」
そんな経験は誰にでもありますよね。モチベーションが上がらない状態が続くと、勉強や仕事の効率が落ち、自己嫌悪にも繋がってしまいます。
大切なのは「やる気が出るのを待つ」のではなく、小さな工夫でモチベーションを取り戻す仕組みを作ることです。
この記事では、モチベーションが下がる原因を整理したうえで、今日から試せる5つの解決方法を紹介します!
モチベーションが上がらない原因とは?

目標が曖昧になっている
「なぜやるのか」が不明確だと、やる気は生まれません。
ゴールのないマラソンをやりたいと思う人はいませんよね。
目的があやふやだと行動の意味を見い出せず、モチベーションが維持できません。
環境や習慣が整っていない
散らかった机やスマホの通知など、集中を妨げる要素があるとモチベーションが削がれやすくなります。
僕はしばらく読んでいなかった漫画が目に止まるとついつい読んでしまいます。
やらなければならない作業をしているときはなおさらですよね。
環境の乱れは心の乱れに直結します。
他人と比較しすぎる
SNSで「毎日努力している人」を見たり、周囲の成果と自分を比べすぎると、「自分なんて…」と落ち込んでしまいます。
僕も、Xで同じ時期に始めた別のアカウントがすごく伸びているのをみたりすると、少し落ち込んでしまいます。
他人との比較はモチベーションを下げる最大の要因のひとつです。比べるべき相手は他人ではなく「昨日の自分」です。
モチベーションが上がらないときに試したいこと5選

小さな行動から始める
大きな目標に取りかかろうとすると何から始めて良いのかわからず「面倒だ」と感じやすいものです。
そんなときは「まずは5分だけ机に向かう」「1ページだけ読む」など、小さな行動から始めてみましょう。行動を起こすことで脳が活性化し、自然とやる気が湧いてきます。
そういう状態を作業興奮といいます。
人間の脳は行動を始めてからある程度の時間が経過すると興奮状態になります。この興奮状態になると最初は嫌だった作業でも続けることができるのです。
これを知っているだけでも、行動へのハードルは下がりますよね。
目標を明確にする
例えば「資格試験に合格する」という目標をもったのなら、「今日は過去問を10問解く」という短期目標を設定しましょう。
目的が具体的であればあるほど、行動に意味を感じられ、モチベーションを維持しやすくなります。
環境を整える
モチベーションが上がらないときは、環境を変えるのが効果的です。
- 机を片付ける
- カフェや図書館に移動する
- スマホを手の届かない場所に置く
このように「やらざるを得ない環境」を作れば、意志の力に頼らず自然に行動を始められます。
タスクを分割する
「やることが大きすぎる」と感じるとモチベーションは下がりやすくなります。そこで、作業を小さなタスクに分けましょう。
例:レポート作成
- 構成を考える
- 参考資料を集める
- 集めた資料を少しずつ読み込む
- 1段落だけ書いてみる
このように小さな達成感を積み重ねることで、自然とやる気が継続します。
他の人と共有する
SNSや友人に「今日はここまでやる!」と宣言すると、責任感が生まれてやる気が出ます。
配信者に有言実行ができる人が多いのもこの原理ですね。
特に同じ目標を持つ仲間と励まし合うと、モチベーションはさらに維持しやすくなります。
やってはいけないNG行動
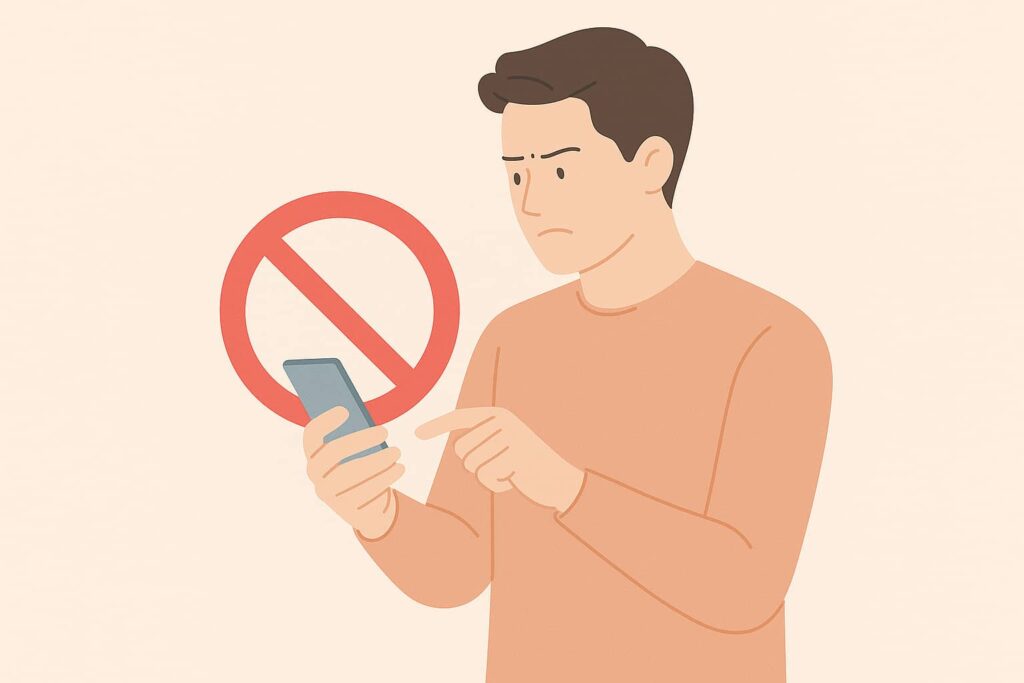
SNSや動画を延々と見る
気分転換のつもりが、逆にやる気を削ぐ原因になります。
好きな動画をみたりすることはリラックス効果がありますが、長時間の視聴は禁物です。
情報過多は集中力を下げ、さらにモチベーションを奪います。
やる気が出るまで待つ
「やる気が出たらやろう」では永遠に行動できません。
「明日やろうは馬鹿野郎」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
今できない人は、一ヶ月経っても一年経っても行動できるようにはなりません。
小さな行動をきっかけにしかモチベーションは戻らないのです。
他人と比較しすぎる
先ほども解説しましたが他人の成果と比べるほど、自己嫌悪に陥りやすくなります。
見るべきは「昨日の自分」との違いです。小さな前進でも成長できていれば十分です。
今回の勝ち組への進捗
モチベーションが上がらないときに試したいことは次の5つです。
- 小さな行動から始める
- 目標を明確にする
- 環境を整える
- タスクを分割する
- 他人と共有する
そしてやってはいけないことは
- SNSを延々と見る
- やる気が出るのを待つ
- 他人と比較しすぎること
上記3つです。
モチベーションは「気持ち」ではなく「仕組み」で作るものです。小さな工夫を積み重ねて、自然とやる気が戻る環境を整えていきましょう!






