フレーミング効果とは?心理学が明かす人の判断を左右する魔法の枠組み
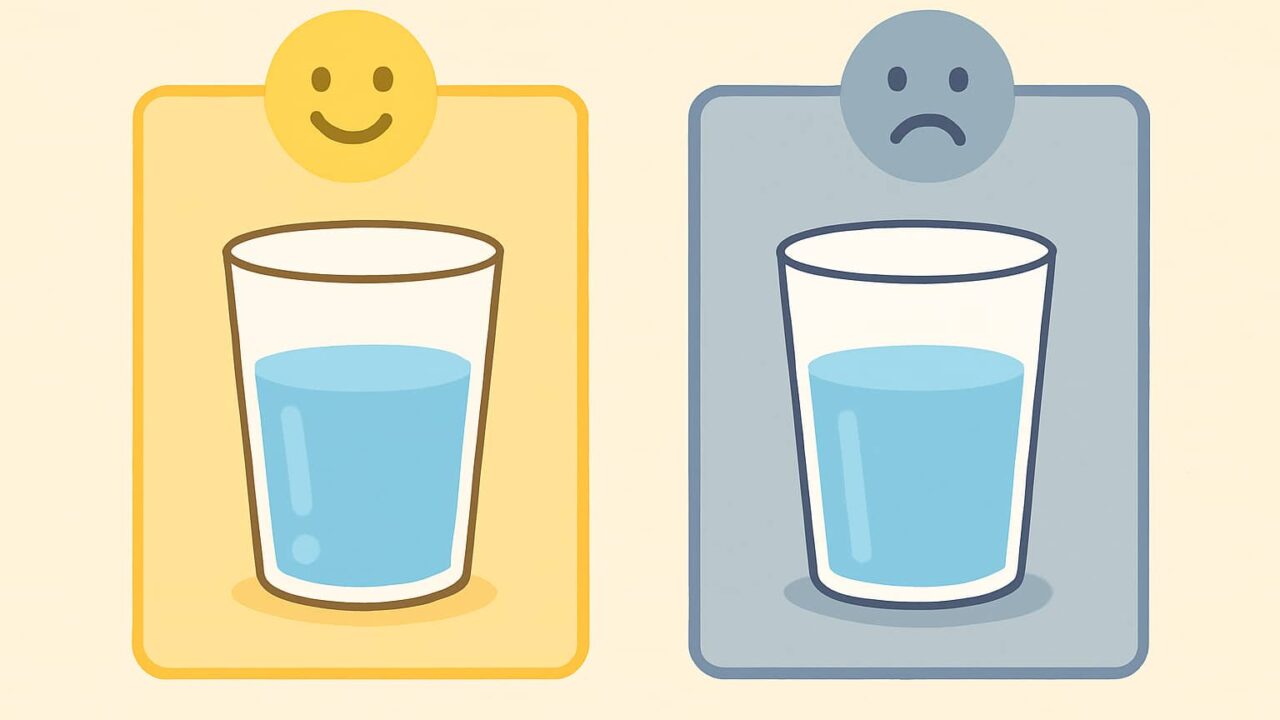
みなさんは「同じ事実なのに言い方で印象が全然違う」と感じたことはありませんか?
たとえばスーパーで「脂肪分20%」と「脂肪分80%カット」と書かれている商品があるとします。
どちらも意味は同じなのに、不思議と後者のほうが魅力的に見えてしまいますよね。
これは心理学でフレーミング効果と呼ばれています。
人は「事実そのもの」よりも、「どう表現されているか」で意思決定を変えてしまいます。
この記事では、フレーミングの仕組みや具体例、メリット・デメリット、そして上手な使い方を徹底解説します。
読めば今日から「言葉の選び方」で人生でちょっと得をする視点が身につきます!
フレーミング効果とは?
定義
フレーミング効果とは、同じ情報でも提示の仕方によって人の判断や行動が変わる現象のことです。
行動経済学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーによって提唱されました。
プラスフレームとマイナスフレーム
- プラスフレーム:「この薬を飲めば90%の人が助かります」
- マイナスフレーム:「この薬を飲んでも10%の人は助かりません」
意味は同じでも、前者のほうが安心感を与えます。
こうして、人は合理的に判断しているつもりでも「言葉の枠組み」に影響されてしまうのです。
フレーミング効果の具体例

ビジネスやマーケティング
- 「この保険に入れば年間10万円の節約!」
- 「この保険に入らないと年間10万円損します!」
人は「損を避けたい」という心理が強いため、後者のほうが契約率が上がることがあります。
医療や健康
「治療後の生存率90%」と言われると希望が持てますが、「死亡率10%」と言われるととても怖く感じますよね。
医療現場でもフレーミングが大きな影響を与えます。
日常生活
- スーパーの「残りわずか!」セール
- ダイエット商品の「成功者の声」
スーパーのPOPの文言につられてついつい買ってしまった経験、ありませんか?
フレーミング効果は日常的にあらゆる場面で使われています。
僕は「残りわずか」という言葉に弱く、結構大きめの豚バラ肉を4パックまとめ買いした過去があります…。冷凍庫がパンパンになってしまいました笑
フレーミング効果のメリット

説得力が高まる
相手にポジティブに響く表現を選ぶことで、提案が受け入れられやすくなります。
どんなものごとでも前向きな言葉は行動を後押しします。
行動を促進できる
フレーミング効果は、人の心理に「背中を押す力」を与えてくれます。
同じ内容でも、伝え方次第で「やってみようかな」と思わせることができるのです。
健康習慣:
- 「運動をしないと病気になるかもしれない」
よりも - 「毎日10分運動すると、10年後も健康でいられる」
後者のほうが「やってみよう」と思いやすいですよね!
学習や勉強:
- 「勉強しないと試験に落ちるよ」
よりも - 「少しずつ勉強すれば合格に近づけるよ」
同じアドバイスでも、モチベーションに大きな違いが生まれます。
ビジネス現場:
- 「失敗したらどう責任を取りますか?」
よりも - 「成功すれば売上アップのチャンスです」
前向きなフレームに変えることで、チームの空気や行動スピードまで変わるのです。
このようにフレーミングは「やらなきゃ」という義務感ではなく、「やってみたい」「やったら得しそう」という前向きな感情を引き出すことで、人を自然に行動へ導く効果があります。
コミュニケーションがスムーズになる
フレーミングを意識して相手が受け入れやすい表現に言い換えるだけで、会話がスムーズになります。
例えば職場でのシーン:
- 「この提案をしないと失敗するかもしれません」
よりも - 「この提案をすれば成功の可能性が高まります」
と伝えたほうが、相手は前向きに話を聞いてくれます。
また、家庭内でも同じです。
「まだ片付けてないの?」よりも「片付けてくれるとすごく助かるよ!」と声をかけたほうが、ケンカになりにくいのは言うまでもありませんよね!
普段の指導でも、「はやくやらないと怒るよ!」よりも「はやく終わらせて休憩しよう!」と声をかけた方が子どもは前向きに動いてくれます!
フレーミングは、相手に行動を促すだけでなく、人間関係を円滑にする潤滑油にもなります!
フレーミング効果のデメリット

誤解を招くリスク
フレーミング効果は「言葉の切り取り方」で相手に良い印象を与えられる便利なテクニックですが、同時に誤解を招く危険性も含んでいます。
情報の偏りで真実が伝わらない
事実は同じでも、表現によって「別の意味」に感じられることがあります。
- 「成功率90%」と聞くと安心できますが、「失敗率10%」と伝えると怖くなる。
→ メリットデメリットの両方を伝えないと、相手は一面的な理解しかしません。
過度に期待させてしまう
商品やサービスを「〇〇をすれば必ず結果が出ます!」とプラスのフレームだけで表現すると、相手が過度に期待してしまい、結果が伴わなかったときに「だまされた」と不信感につながるリスクがあります。
ネガティブに受け取られるケース
相手が敏感な状況だと、少しの表現の違いで「責められている」と感じてしまうことも。
例:
- 「やらなかったら失敗しますよ」→ 脅迫的に聞こえる
- 「やれば成功の可能性が高まりますよ」→ 励ましに聞こえる
コミュニケーションの信頼を損なう
フレーミングを多用して「都合のいい部分だけを強調している」と思われると、逆に信頼を失いかねません。
特にビジネスや医療の場面では「伝え方」と同時に「正確さ」も重要です。
いいことばかりを伝えられるとちょっとしたデメリットでも「ん?」と引っかかってしまいますよね。最初にデメリットの部分もきちんと伝えるというのは信頼関係を築くうえでとても大切です!
フレーミング効果は「伝え方次第で誤解を生む諸刃の剣」です。
プラスの効果を狙うときも、相手に不必要な誤解を与えないように 「全体像をきちんと伝えるバランス感覚」 が欠かせません。
操作的になりやすい
過度に利用すると「相手を誘導するテクニック」として不信感を持たれることもあります。
感情に流されやすくなる
「お得に見えるから」という理由で冷静な判断を失い、無駄な買い物をしてしまうことがあります。
僕の「豚バラ肉事件」はまさにコレです笑
フレーミング効果を上手に活用する方法
ポジティブに言い換える
「やらなきゃ失敗する」よりも「やれば成功できる可能性がある」と伝えましょう。
自分自身に使う
ダイエット中に「お菓子禁止」ではなく「お菓子を控えて健康な自分に近づく」と考えると続きやすいです。
相手の立場を想像する
相手がどう受け取るかを意識して表現を選ぶことで、信頼関係が深まります。
子どもにトレーニングをさせたい時は「筋力をつけなさい!」よりも「今はしんどいけど、後で必ず役に立つから頑張ろう!」といった方がしっかり取り組んでくれます!
今回の勝ち組への進捗
フレーミング効果とは、言葉の表現次第で人の判断や行動が変わる心理効果です。
- ビジネスや医療、日常生活のあらゆる場面で働く
- うまく使えば説得力が増し、行動も促せる
- 情報の偏りは誤解に繋がるので使い方には注意
言葉は「事実そのもの」以上に力を持っています。
ぜひ今日から「伝え方のフレーム」を意識して、あなたの人生を豊かにしましょう!





