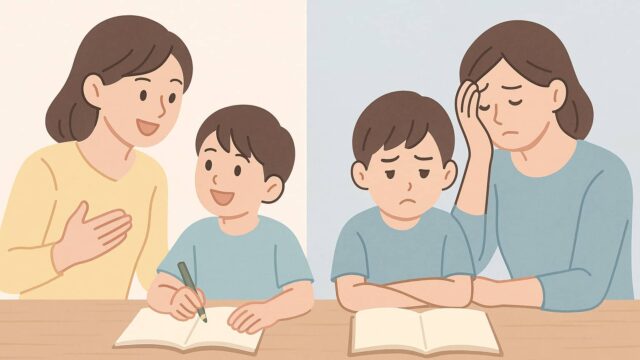完璧主義の人の手の抜き方|疲れない働き方を解説
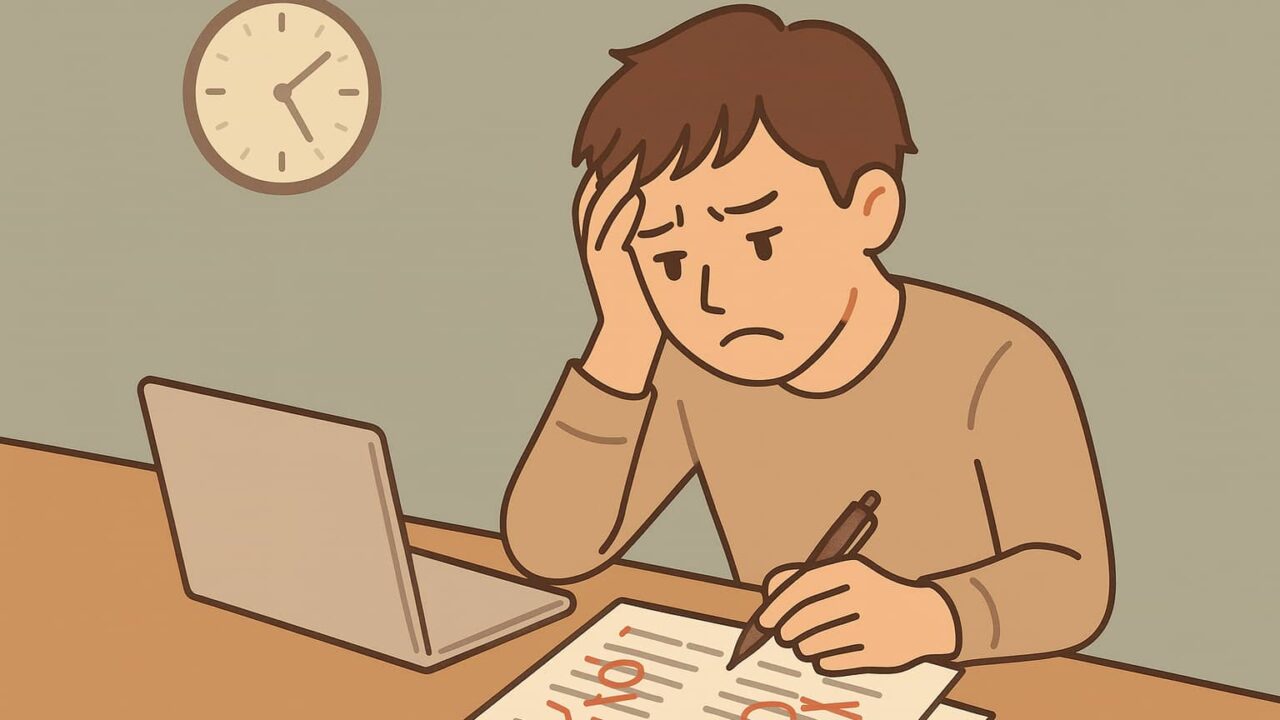
「このままじゃ苦しいのは分かってる。でも手を抜いた瞬間に自分の価値が下がる気がして怖い」
——そんな思いを抱えたまま、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
完璧主義で悩んでいる人は、
- 完璧主義の弱点は何なのか
- そもそもどういう特徴なのか
- 仕事ではどこまで力を抜いていいのか
- やめる方法はあるのか
というような疑問を持っていると思います。
この記事では、手を抜くのが上手い人に共通して見られる行動パターンを整理し、「手を抜く=悪いこと」という思い込みをやわらげつつ、試しやすい工夫や考え方を体系立ててまとめています。
なんでも完璧にしようとすると先に進まないし、悩みも増えますよね…。今回は完璧主義の人が少しでも楽になるよう様々な情報をまとめました!
免責事項:
本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療・法的助言ではありません。強い不安、睡眠障害が続く、業務遂行が難しいほどの消耗などがある場合は、医療機関や専門相談窓口にご相談ください。
緊急時の対応:
生命・安全に関わる切迫した状況では、直ちに119番等の緊急連絡先へ。
記事のポイント
- 完璧主義の実態とリスクの見える化
- 良い手抜きと悪い手抜きの違いを理解
- 仕事で使える具体的な省力化の手順
- 今日から試せる習慣化のコツ
完璧主義の人の手の抜き方の全体像
- 完璧主義の特徴を客観整理
- 完璧主義の弱点は何?
- 完璧主義はなぜしんどいのか?
- 完璧主義をめんどくさいと感じてしまう
- できないのに完璧主義に陥ってしまうのはなぜか?
完璧主義の特徴を客観整理

完璧主義の特徴は、「基準が高い人」といった一言ではまとめきれません。
仕事や勉強の場面では、できた部分よりできていない部分に目が行きやすい、全体より細かい部分を優先しがち、ミスを避けようとして動き出すまでに時間がかかる、などの傾向が見られることがあります。
特に「減点の視点」が強くなると、できたところの価値が自分の中で小さく扱われてしまい、自信が育ちにくくなるとも言われています。
努力の質が低いという意味ではなく、仕事が実際には「目的に合っているか」と「時間や労力に見合っているか」で評価される場で、そのバランスが崩れやすいという話です。
現場では、チェックリストが全部埋まらないと提出しない、必要のない見た目の調整に時間をかける、レビュー前に自分で直し続けて終わらない、といった動きとしてあらわれることがあります。
一見まじめで丁寧な姿勢に見えても、締切や他の人との連携を考えると、必要以上の仕上げが足かせになる場合もあります。また、「全てやり切って初めて合格」という考え方になると、途中で得られる気づきや試行錯誤の価値が見えにくくなり、改善の回転が遅くなることもあるようです。
一方で、完璧主義には、丁寧さ、誠実さ、仕上げの正確さといった強みもあります。
問題になるのは性格そのものより、それをどう運用するかの部分です。たとえば、要件をA(絶対に必要)、B(できれば)、C(なくても良い)に分けておき、Aができたら一度提出して良い、Bは余力があれば、Cは次回に回す、といった線引きをしておく方法があります。
また、できているところに点を足していく「加点」の見せ方にすると、進んでいる実感が得やすくなり、自信が保たれやすくなるとも言われています。
よく見られる思考パターン
| パターン | 特徴 | 影響 |
|---|---|---|
| 白黒思考 | 合格か失敗の二択で捉える | 中間解を選びにくい |
| 過度な自己批判 | 小さなミスを全体否定へ拡大 | 自信と行動量の低下 |
| 過剰な基準設定 | 必要以上の品質ラインを採用 | 工数増・期限遅延 |
MVP(最小実行版)という言葉は専門的に聞こえますが、「まずは必要最低限の形で一度出してみる」という考え方を指しています。
いきなり完璧を目指すのではなく、まずは目的に合っているかどうかを早めに確認し、その後に必要な改善を重ねていくためのやり方です。
また、API(異なるソフト同士をつなぐ仕組み)や、作業を自動化するツールなどを使うことで、人の手で細かく対応し続ける必要がないようにする取り組みも、完璧主義の負担を和らげる助けになると考えられています。
これらは「性格を直す」という発想ではなく、働く環境の側を整えて、丁寧さを保ちながらも無理なく進められる状態をつくるための現実的な工夫といえそうですね!
完璧主義の弱点は何?

完璧主義の弱点としてよく指摘されるのは「かけている時間や労力の割りに合っているかを見落としやすいこと」と「状況が変わっても自分の基準を変えにくいこと」の二つにまとめられます。
前者については、仕上がりを良くしようとするほど時間と集中力が必要になり、そのぶん他の仕事に手が回らなくなる可能性があります。
しかも減点の視点が強いままだと「まだ足りない部分」ばかりに注意が向き、使っている時間や体力のコストに意識が届きにくくなることがあります。
その結果、一つの作業に力を注ぎすぎて、他の仕事が後回しになり、全体としては効率が下がるという構図になりがちです。
後者については、要件や締切が途中で変わったり、関係者の合意ラインが調整されたりしても、心の中の理想像が動かないために、直すべきタイミングを逃しやすいという面があります。これが、判断や提出の遅れにつながることがあります。
実務の場では、レビュー前に何度も自分で直し続ける、提出後の指摘を過度に恐れて遅らせる、締切直前に微調整を繰り返す、といった動きとして表れることがあるとされています。
こうした行動は真面目さの裏返しとも言えますが、プロジェクト全体で見ると他の人の作業待ちが発生し、全体の進みが遅くなる要因にもなり得ます。
さらに提出が遅れると、フィードバックを受ける回数が減り、改善のスピードも落ちてしまうという逆転現象が起こりやすくなります。
対処の軸としては、基準を自分の頭の中だけで持つのではなく、外側に出して共有しておくことが有効と言われています。
例えば、A=絶対に必要な条件、B=できればやりたい範囲、C=今回は見送る範囲、のようにレベル分けをして、Aが満たされたら一旦提出して良いという線引きをしておく方法があります。
あわせて、修正は2回まで・1回は15分までといった上限を先に決めておくと、終わりどころが見えやすくなります。チェックは減点方式ではなく、できた項目に点を足していく見せ方にすると、提出の判断がしやすくなります。
さらに、タスク開始前にレビューの日程だけ先に固定しておくと、自主修正のループが走りにくくなり、判断の遅れを防ぎやすくなります。
注意
締切直前の過剰修正や意思決定の遅延は、チーム全体のスループットを下げます。必要十分条件の定義と修正上限の設定を先に共有し、加点方式のチェックリストで合格判定することで、過剰品質の暴走を防ぎやすくなります。
また、見えづらくなりがちな負担を把握するために、たとえば「その作業に何時間かかったか」「何回修正したか」「レビューにどれだけ待ち時間が発生したか」といった項目を簡単に記録しておく方法も考えられます。
あとから振り返れる形にしておくと、「どこにどれだけ手間がかかっていたのか」「本当にその労力が見合っていたのか」といった感覚が少しずつ育ちやすくなります。
定期的に作成したデータを見返して、次に同じような作業をする際の基準や進め方に反映していく仕組みをつくることで、完璧主義の負担になりがちな部分が、次回への改善材料として活きてきます!
完璧主義はなぜしんどいのか?

完璧主義で疲れてしまう背景には、「ずっと緊張が抜けない状態」と「いつまでたっても終わらない感覚」の2つが関わっていると言われています。
前者は、失敗を避けることを最優先にすると気が張った状態が続き、少しのミスの気配にも強く反応してしまうことで、精神的な疲れが積み重なりやすいという見方があります。
後者は、どこで終わりにするかが決まっていないために「まだできるはず」「まだ足りない気がする」と考え続けてしまい、自分で区切りを出せないことから来るものと考えられます。
どちらも、あらかじめ終わり方の基準が言語化されていないことや、できている部分より足りない部分の方を重たく見がちな評価の癖が背景になっていると説明されることがあります。
国際的な職業ストレスの枠組みとして、WHOのICD-11では、長期間コントロールされない仕事上のストレスと関連してバーンアウトが取り上げられています。
そこでは、感情的な消耗感、仕事から気持ちが離れていくこと、仕事の手応えの低下などが特徴として挙げられています(出典:World Health Organization「ICD-11におけるバーンアウトの定義」)。
この定義は完璧主義そのものの説明ではありませんが、実務で見られる「張り詰めたままの緊張」や「終えられない感覚」が、職場のストレス環境によって強まる可能性が示唆されているとも考えられます。
したがって、個人が気持ちで踏ん張るのではなく、仕事の基準や進め方そのものを整えることが一つの現実的な選択肢とされています。
実務上の対策としては、いつ始めるか(開始基準)と、どこで終わりにするか(終了基準)をあらかじめ明文化しておく方法が挙げられます。
たとえば「必須条件がそろったら提出する」「誤字脱字と体裁のチェックは10分以内まで」「細かい修正はレビュー後に回す」などのルールを先に決めておくやり方です。
チェックリストも未達探しではなく、できている項目を積み上げていく加点方式にしておくと、提出の判断がしやすくなる場合があります。
さらに、修正回数(例:2回まで)や、1回あたりの修正時間(例:15分まで)に上限を設けると、気持ちではなく事前に決めた合意事項に沿って終わりを判断しやすくなると言われています。
終了基準の例
- 要件を満たすチェックリストを満点でなくても通過させる
- 上司・クライアント合意の合格ラインを超えたら提出
- 修正回数の上限を事前に設定(例:2回まで)
さらに、負担の状態を定期的に見直すことも大切だとされています。
たとえば、1週間ごとに「作業にかけた時間」「どれくらい頭が疲れたと感じたか」「最近の睡眠の調子」といった簡単な項目をメモしておくと、自分の働き方の傾向をつかみやすくなります。
そのデータをもとに、「午前は集中力が必要なAの仕事に使い、午後はルーチン的なBの作業をする」といった形で、時間帯ごとに集中のピークを分ける工夫も考えられます。こうした調整を続けることで、日によって大きく波がある“しんどさ”を少しずつならしていけるかもしれません。
最終的な目標は、自分の中にある理想像だけを基準に頑張るのではなく、外に出して共有できる合意の基準を使って仕事を終わらせることです。その方が、完璧主義の良さである丁寧さや注意深さを保ちながらも、必要以上に気を張らずに済み、安定したパフォーマンスに近づける可能性があります。
完璧主義をめんどくさいと感じてしまう

「めんどくさい」という感覚は、怠け心というよりも「かけている手間と、そこから得られる価値のバランスが崩れているサイン」と捉えられます。
特に完璧主義の状況では、作業そのものが難しいというよりも、「どこまで仕上げればいいのか」という基準が曖昧なせいで考える回数が増え、その判断にエネルギーが奪われやすくなってしまいます。
たとえば提出の条件がA(必須)B(できれば)C(今回は不要)のように分かれていないと、その都度考え直す必要が出てきて、着手するだけでも心の負担がかかります。
加えて、必要な資料の場所が分かりづらい、ファイル名にルールがなく最新版が判別しにくい、レビュー基準が人によって違う、といった環境要因が重なると、「考えるだけで疲れる」という状態が積み上がりやすくなります。
こうした環境では、「やったあとの成果」よりも「やるまでの手間」のほうが意識に強く残りやすく、その結果として「めんどくさい」という印象が強まりやすいと考えられます。
こうした背景には、人が使える集中力や判断のエネルギーには限りがある、という前提があります。
人は判断を繰り返すほど判断の質が落ちやすい、という考え方は行動科学の分野でも広く取り上げられています。
完璧主義が進むと、一つ一つの判断を細部まで精密に行おうとしてしまい、「どこはざっくりで良いか」「どこだけ丁寧にやるべきか」という切り分けが機能しにくくなります。
また、資料を作る目的が「説明や意思決定を助けること」だったはずなのに、「見た目をキレイに仕上げること」自体が目的になってしまうと、成果に関係の薄い手直しが増えて、手間と効果のつり合いが崩れやすくなります。
言い換えると、「めんどくさい」を減らすというのは、気合いで乗り越えることではなく、「判断の回数」と「判断の重さ」を減らす設計に切り替えることでもあります。
たとえば、提出の終了ラインを先に決めておく、検索の手間を減らすためにファイル名と保存場所を統一しておく、レビュー項目をテンプレート化して人によるブレを減らす、などの環境を整える工夫が優先されます。
こうした仕組みの側から見直すことで、「めんどくささ」が減り、同じ努力でも前に進みやすくなります。
めんどくささを生む要因の棚卸し
| 領域 | 主な要因 | 改善の起点 |
|---|---|---|
| 基準 | 提出ライン不明・合格点不統一 | A/B/Cの優先度で明文化 |
| 情報 | 最新版不明・検索に時間 | 命名規則と保管場所の固定 |
| 工程 | レビュー観点が属人化 | 観点チェックリストの標準化 |
| 心理 | 白黒思考・過度の自己批判 | 加点方式で進捗を可視化 |
ここで関連する用語としてWIP(Work In Progress)について触れておきます。
WIPとは「いま同時に抱えている作業の数」を指す言い回しです。一般的には、同時に進める仕事が増えるほど頭の切り替え回数が増え、その分ゴールにたどり着くまでの時間が延びやすい、と説明されることがあります。
完璧主義が強いと、一つずつ終わらせる前に全てを高い水準にしようとしがちで、その結果としてWIPが増え、「どれも終わらない」「どれも進まない」といった感覚が強まる場面があるようです。
これを防ぐ方法としては、WIPに上限を設けるというやり方がよく紹介されています。たとえば「同時に抱える仕事は3件まで」「レビュー待ちは2件まで」など、上限を数字で決めておくと、判断の回数を減らしやすくなり、エネルギーを成果につながる部分に集中しやすくなるという考え方があります。
こうした視点に立つと、「めんどくさい」というのは気合いの問題ではなく、仕事の設計や扱い方の問題として見ることもできそうですよね!
できないのに完璧主義に陥ってしまうのはなぜか?

この言い回しは強めですが、「能力がない」という話ではないと考えられます。多くの場合は、自分の今の経験値と求められている完成度の差が大きいのに、最初から完璧な形で仕上げる前提で動き始めてしまう設計上の問題が背景にあります。
途中で形を出さず、いきなり完成形だけをゴールに置いてしまうと、「失敗の確率が高い状態でしかスタートできない」構図になり、先延ばしがむしろ合理的に見えてしまう状況が起こりやすくなります。
その結果、着手が遅れ、締切直前に詰め込むしかなくなり、仕上がりが不十分になり、その経験が「できないくせに完璧主義」という評価につながる……という流れが生まれやすくなります。
ここから抜け出すための鍵として「段階を踏んで進める仕組みを先に決めておく」という考え方があります。
MVP(最小限の形)の提出を認める、途中レビューを入れる、評価を減点ではなく加点で見る、修正の回数や時間をあらかじめ区切っておく、などのやり方がその例です。
たとえば、新しいテーマで調査記事を作る場合、いきなり完成版を作ろうとするのではなく、「想定見出しの案」「必要になりそうな出典候補」「ざっくり構成」の順に中間物を出してチェックを受ける方法があります。
こうすると、方向のズレを早めに修正しやすくなり、無駄な手戻りが減ります。そのうえで、自己評価のしかたも変えます。
できていないところではなく、「出典が一次情報に基づいている」「統計の年次が明示されている」「専門用語に初出の説明が入っている」など、できている要素にポイントをつける形(達成スコア)にすると、進んでいる実感が得られやすくなります。
大事なのは、「提出できるかどうか」を自分の理想イメージではなく、外に出した共通ルールで判定する流れに乗せることだと言われています。
| 局面 | つまずきやすい挙動 | 設計での回避策 |
|---|---|---|
| 開始前 | 最終形が見えず着手が遅れる | MVP範囲と提出日時を先に固定 |
| 途中 | 細部に固執し全体が停滞 | レビュー観点を3点に限定 |
| 提出直前 | 終わりを決められない | 修正回数2回・1回15分の上限 |
補足として、ROIという言葉にふれておきます。
ROIは「かけた労力や時間に対して、どれくらい成果が戻ってきたか」を見る考え方です。完璧主義に陥ると、この効率が下がりやすいと指摘されることがあります。
特に、初期段階で軌道修正の余地が大きいタイミングを逃してしまうと、少ない努力で方向を整えられたはずのチャンスを失うことになります。
その逆に、MVP(最小限の形)をまず出し、レビューを受けて改善する、という短いサイクルを回す方法は、早い段階で修正が利きやすく、限られた労力で成果に近づけるという意味で、効率を高める考え方として紹介されています。
ここで伝えたいのは、「その人に能力があるかないか」ということではなく、能力を成果に変換するための仕組みや手順を整えることに焦点を移すという視点です。
基準の置き方や進め方を工夫することで、同じ力でも結果の出方が変わる可能性がある、という捉え方が、完璧主義の悪循環から抜ける道筋として提案されています!
完璧主義の人に伝えたい手の抜き方の実践術
- 仕事の手の抜き方の見極め方
- 手を抜くのが上手い人の習慣
- 手を抜くのは悪いこと?
- 完璧主義をやめる方法の基本
仕事の手の抜き方の見極め方

物事をどこまでやるか判断するときの出発点として、「その作業が成果にどれくらい効いているか」を先に見ておくと整理しやすくなります。具体的にはタスクを三つに分けます。
- A:これができていないと成果そのものが成立しないもの
- B:できていると成果が良くなるが、別のやり方でも補えるもの
- C:やらなくても大きな影響は出にくいもの
Aは丁寧に、Bは効率よく、Cは思い切って減らす、という考え方にすると、「必要十分な品質」で止めやすくなります。
ここで役立つのが、あらかじめ「やらない」と決めておく項目をリストにしておく方法です。A/B/Cを決める場で同時に「今回はCはやらない」と宣言しておくと、後から迷う回数が減り、「何度も考え直す疲れ」を減らせます。
さらに、「Aが満たされていて、誤字脱字と体裁チェックを通過したら提出する」など、終わりの条件を先に決めておくと、必要以上のやり込みに入りにくくなります。
実務では、判断のばらつきを減らすために数値の指標を使う方法もあります。
たとえば「1つのタスクに何時間かかったか」「レビューでの指摘がどれくらい出たか」「テンプレ化して次も使える内容か」といった指標をKPIとして共有し、品質・時間・納期の三つの観点で揃えるやり方です。
品質は必要十分の基準を満たすこと、時間は使いすぎないよう上限を決めること、納期は遅れないよう前倒し提出を基本とすることなどをチームで確認しておくと、判断が揃いやすくなります。
補足として、クリティカルパス(最終的な納期を決めてしまう一連の工程)は、Aに当たる「外せない部分」として扱われることが多いです。これに含まれない装飾的な作業はB/Cに分類し、簡素化・委任・自動化などを検討する対象になります。
このように「何を守り、どこで力を抜くか」を先に整理しておくことが、完璧主義で疲れやすくなる状況を緩和する手がかりになると考えられています。
| 観点 | 問い | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 目的適合 | 目的に直接必要か | 必要でなければ除外 |
| 再利用性 | 次回以降も使えるか | テンプレ化を優先 |
| 代替可能 | 自動化・外部化できるか | 自動化や委任を検討 |
| 納期影響 | 遅延リスクがあるか | クリティカルパスは厳密 |
API(異なるソフト同士をつなぐ仕組み)やRPA(同じ作業を自動でこなす仕組み)は、「やったほうがよいけれど人の手で丁寧にやる必要はない」領域を短縮する代表的な方法として紹介されています。
いきなり高度な自動化に踏み込む必要はなく、まずはチェックリストやテンプレートなどの手動でできる簡易化から始め、効果が見えた部分だけを自動化の対象にしていくと、導入の負担を小さくしやすいとされています。
また、長時間の働き方が続く場合には、体調の面に気を配る必要があります。
厚生労働省は、過重な労働による健康上の不調を避けるため、残業時間の抑制や医師による面接指導などの対策が必要になるケースがあることを示しています(出典:厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」)。
成果を出すことと健康への配慮を両立できるラインをあらかじめ設計しておく考え方が大切です!
手を抜くのが上手い人の習慣

手を抜くのが上手い人は、決してサボっているわけではなく、「どこまでやれば十分か」を先に決めてから動く人たちだと捉えることができます。
特徴としては、
- 着手前に時間をかけて設計する
- どこで終えるかを先にすり合わせておく
- 細かい改善は提出後に回す
といった三つの段階を繰り返し運用している点が挙げられます。
あらかじめゴールを共有し、途中では余計な判断や工程をそぎ落とし、終わらせ方を先に決めて修正のループを断ち切ることで、「迷う」「やり過ぎる」「やり直す」といった完璧主義にありがちな負担を小さくしていくイメージです。
もう一つの特徴は、「どこに努力を使うか」を選んでいる点です。成果に直結するAの仕事にはしっかり集中し、B/Cの仕事はテンプレや過去資料を使い回す、人に任せる、自動化するなど、抱え込まない工夫をしています。
レビューの観点を3つ以内に絞るなど、判断の出口を減らすことで迷いを少なくする手法も目にします。
さらに、毎週ふりかえりを行い、作業時間・指摘の数・再利用率といった記録を振り返って、「次に直すのは1点だけ」と決めると、改善が負担になりにくく習慣として続けやすくなります。
- ゴール定義と終了基準の事前合意
- テンプレート・チェックリストの活用
- 人に任せる判断と引き継ぎの整備
- 週次の小さな改善(工程の削除・結合)
このような考え方は、完璧主義の長所を残しつつ負担を減らす方法として用いられます!
合格ラインの事前合意 は過剰品質を止める最短のレバーです。評価を加点方式に変えると、進捗の自覚と心理的余裕が同時に確保されます。
手を抜くのは悪いこと?

手を抜くことが「悪い」と見られる場面は、手を抜いたせいで品質が明らかに落ちた結果が目に見えたとき、という説明がしやすいかもしれません。
逆に、安全・法律・倫理・信頼など守るべき前提が保たれたうえで、成果として必要な条件がきちんと満たされているなら、その手の抜き方は怠けではなく「無駄を省いたやり方」と考えることもできます。
判断は気分ではなく、
- 目的を満たしているか
- それによって大きな損失につながらないか
- 同じ品質をもう一度出せる仕組みか
といった観点で外側に出して確認する方がブレにくくなります。
いわゆる「良い手の抜き方」は、必要な品質を守りつつ工程を簡単にする・標準化する・再利用する、といったやり方を指します。
一方で、「悪い手の抜き方」は、本来必要な品質が落ちる省略や、安全・法律・倫理といった土台を崩す行為を含みます。
特に医療や建設、公共インフラのように安全面の制約が強い領域では、軽くできる作業(C領域)は簡素化の対象にしても、外してはいけないA領域は残す必要があるという考え方が一般的に採用されやすいです。
法律や安全に関わる基準(例:産業安全衛生に関する規定など)は違反した場合のリスクが大きいため、「ここは削れない部分」とあらかじめ線を引いて共有しておくことで、判断ミスを減らしやすくなります。
| 区分 | 良い手抜き | 悪い手抜き |
|---|---|---|
| 目的整合 | 成果要件を満たすための簡素化 | 成果要件を満たさない短縮 |
| 品質 | 必要十分の品質を担保 | 安全・法令・倫理を損ねる |
| 再現性 | 標準化し再利用可能 | 属人的で再現できない |
安全・法令・倫理 を含む基準は簡素化の対象外。線引きは着手前に外化し、レビューで共有してから実行へ。
完璧主義をやめる方法の基本

完璧主義を直そうとするとき、「性格そのものを変える」という発想よりも、「やり方の仕組みを変える」という視点に切り替えるほうが実務には落とし込みやすいと言われています。
見直す軸としては、
- 考え方の持ち方
- 仕事の進め方
- 環境の整え方
の三つに分けると整理しやすくなります。
考え方の面では、「できていないところ」よりも「できたところ」に目を向ける加点の見方に切り替えると、自己評価が極端に下がりにくく、取りかかりの遅れも軽減されやすくなるとされています。
行動の面では、完璧に仕上げてから出すのではなく、最小限の形(MVP)をまず提出し、その後レビューで方向を整えながら完成させる流れにすると、手戻りが減りやすいという考え方があります。
環境の面では、人に任せる・標準化する・自動化するなどによって、自分の注意力をすべてで使い切らない仕組みをつくることが効果的とされています。
ここで大切なのは、「気合いで改善する」のではなく、「ルールで支える」ことです。
たとえば、修正回数に上限を決める、1回あたりの修正時間を区切る、提出の合格ラインを先に決めておく、レビュー観点を固定するなど、終わり方を外に出しておくと、迷いが減りやすくなります。
いきなり完璧主義を全部やめる必要はなく、A(絶対に必要なこと)には集中しつつ、B/C(余力でやること・今回は見送ること)は簡素化や後回しを許容するモデルに移すことで、完璧主義の良さである「注意深さ」だけを残しつつ、過剰になりやすい部分だけを外す、という設計も考えられます!
合格点を超えたら自分を褒める小報酬設計は、行動継続を支える技術として有効(報酬による行動維持は行動分析学の基本原理に依拠)。数値化された加点表は行動維持の装置として機能します。
まとめ|完璧主義の手の抜き方
ここまでの内容を振り返ると、完璧主義における「手の抜き方」は、単なる妥協とは違い、「目的に合った形で力のかけ方を整える工夫」と言えます。
やるべきところの品質は保ちながら、時間や集中力などの負担を調整することで、成果は落とさずに消耗を減らす考え方です。
最後に、ここまで触れてきたポイントを実務で使いやすい形に整理しておきます。
- 完璧主義の特徴を理解し、基準運用を柔軟に整える
- 目的と要件を区別して必要十分な品質水準を明確にする
- 終了基準を明文化して修正回数や時間を数値化する
- やらないことリストを作り不要な作業を事前に排除する
- ECRSで工程を点検し削除・結合・交換・簡素化を回す
- 減点ではなく加点方式で進捗と達成を可視化する
- MVP提出を基本にフィードバック改善を繰り返す
- テンプレートとチェックリストで再現性を確保する
- 委任領域を定義して自分の集中資源を守る
- 自動化やツールを導入して手動工程を減らす
- 重要度と緊急度を整理し資源配分の誤りを防ぐ
- 目的整合を軸に良い手抜きと悪い手抜きを判別する
- 合格ラインの事前合意で過剰品質の暴走を抑える
- 中間解を容認し白黒思考から連続的評価へ移行する
- 完璧主義の手の抜き方を習慣化して疲労を軽減する
「手を抜く」というのは価値を下げることではなく、限られた時間や体力を、より意味のあるところに振り向ける考え方です。
完璧主義の中にある丁寧さや責任感を活かすためには、気持ちで頑張るのではなく、終わり方などのルールを外側に用意しておくほうが続けやすいという見方があります。
まず着手しやすい一歩としては、「どこまでできたら終わりにするか」を事前に言葉で決めておくことです。これを続けるだけでも、働き方の体感はかなり変わってくる可能性があります。
完璧主義の手の抜き方を身につけるというのは、努力を短くする話ではなく、努力を長く続けられる形に整える技術だと言えます。
目的にエネルギーを適切に配分できる人ほど、結果として安定して良い成果を生みやすい、という指摘も見られますので、今一度何にエネルギーを使うべきなのかをしっかり見つめ直すことが大切です。
参考文献:
公的機関・公式一次情報
World Health Organization. Burn-out an “occupational phenomenon”: International Classification of Diseases. 28 May 2019.
https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
(Accessed 2025-10-23)
World Health Organization. Burn-out an “occupational phenomenon” — FAQ.
https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/burn-out-an-occupational-phenomenon
(Accessed 2025-10-23)
WHO. International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11).
https://icd.who.int/
(Accessed 2025-10-23)
厚生労働省『過重労働による健康障害を防ぐために』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07041.html
(Accessed 2025-10-23)
Hill AP, Curran T. Multidimensional perfectionism and burnout: A meta‐analysis. Personality and Social Psychology Review. 2016;20(3):269-288.
https://doi.org/10.1177/1088868315596286
(Accessed 2025-10-23)
Stoeber J, Haskew AE, Scott C. Perfectionism and exam performance: The mediating effect of task-approach goals.Personality and Individual Differences. 2015;74:160-164.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.10.016
(Accessed 2025-10-23)
Shanafelt TD, et al. Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Archives of Internal Medicine. 2012;172(18):1377-1385.
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1351351
(Accessed 2025-10-23)
免責事項:
本記事は一般的な情報提供を目的としており、医療・法的助言ではありません。強い不安、睡眠障害が続く、業務遂行が難しいほどの消耗などがある場合は、医療機関や専門相談窓口にご相談ください。
緊急時の対応:
生命・安全に関わる切迫した状況では、直ちに119番等の緊急連絡先へ。