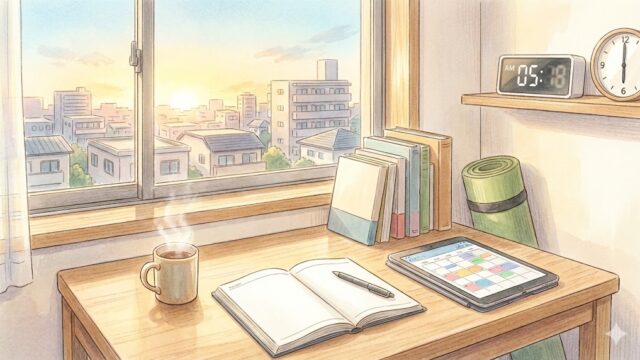人間関係で大切なこととは?5つの基盤と悩み別対処法

こんにちは!スルースのVictory Academy、運営者の「スルース」です。
人間関係について悩みのある方は、今、何かしら人との関わり方で悩んでいると思います。
職場での適切な距離感に戸惑ったり、合わない人とのコミュニケーションに疲れたり、時にはもう全部リセットしたいと感じてしまうこともあるかもしれません。
また、友人関係や家族関係をもっと良好にしたい、という前向きな悩みもあるかなと思います。人間関係は、私たちの生活の質に直結する大きなテーマですよね。
私自身、専門家というわけではないですが、これまで色々な人との関わりの中で、どうすればお互いが心地よくいられるか、たくさん考えてきました。
この問題の難しいところは、相手や状況によって「正解」が変わってしまうことだと思います。
この記事では、私が学んできた人間関係の「土台」となる考え方から、具体的な悩みへの対処法まで、いくつかのポイントに分けて整理してみました。
あなたの悩みを解決するヒントが、きっと見つかるかと思います。
- 人間関係を支える5つの土台
- 職場や友だち、家族との距離感のコツ
- 「疲れた」「合わない」と感じた時の対処法
- 関係修復や「離れるべき人」の見極め方
免責事項:
本記事の内容は、筆者の経験や公的機関等が公開している一般的な情報をもとにしたものであり、
医師・カウンセラー・弁護士など専門家による診断や助言の代わりとなるものではありません。
人間関係の悩みやストレスによって、強い落ち込みや死にたい気持ちが続く場合、
またDVやストーカー行為など身の危険を感じる場合は、
一人で抱え込まず、医療機関・公的な相談窓口・警察等の専門機関にご相談ください。
人間関係で大切なことの5つの基盤

人間関係って、漠然としていて掴みどころがないように感じますよね。しかし、良好な関係には共通する「基盤」のようなものがあるんです。家を建てる時の土台と同じで、ここがしっかりしていないと、ちょっとしたことでグラグラしてしまいます。
ここでは、その「5つの基盤」について整理してみたいと思います。これらは個別に存在するのではなく、お互いに深く関連し合っているんです!
信頼:すべての関係の土台
まず、何と言っても「信頼」ですよね。
これが全ての土台だと思います。信頼がないと、何を話しても疑ってしまったり、安心して関わることができません。
この土台がなければ、他の4つの基盤も機能しないと言っても過言ではない思います。
信頼は2段階あると思っており、最初は「信用」です。
これは「約束を守る」とか「時間通りに来る」「実績がある」といった、客観的な事実や過去の行動に基づく評価です。
「この人は信用できる」というのは、どちらかというと論理的な判断です。
しかし、人間関係で本当に大切なのは、その先の「信頼」、つまり「この人なら大丈夫かも」「この人に任せてみたい」っていう未来への期待感や感情的なつながりだと思います。
「信用」から「信頼」へ
この「信頼」を築くには、やはり言動の一貫性が欠かせません。
言うことがコロコロ変わったり、感情の起伏が激しくて態度が日によって違ったりすると、相手は「予測できない」と感じて不安になってしまいます。
機嫌が良いときは優しいけど、悪いときは無視する、みたいな人とは安心して関われないですよね。
「小さな約束を守る」という地道な「信用」の積み重ねが、やがて「この人なら大丈夫だ」という感情的な「信頼」に変わっていくんだと、僕は考えています。時間や期限を守る、頼まれたことを忘れない、言ったことを実行する。そういった当たり前のことを、誠実に続けることが一番の近道なんです!
信頼構築の第一歩:
信頼は一朝一夕には築けません。まずは「小さな約束」を守り、「言動に一貫性を持つ」こと。これが客観的な「信用」を生み、その蓄積が感情的な「信頼」へと昇華していきます。
共感:違いを乗り越える力

次に大切なのが「共感」や「相互理解」です。
私たちはみんな、育ってきた環境も経験も価値観も違います。だから、意見が食い違うのは当たり前なんですよね。むしろ、違って当然なんです。
ここで大事なのは、「正しい・間違い」の二択で物事を判断しないことだと思います。
自分と違う意見に出会ったとき、すぐに「それは間違ってる」と否定するんじゃなくて、「そういう考え方もあるんだな」「あなたはそう感じるんだな」と、まずはいったん受け止めてみること、これが「相互理解」のスタート地点です。
「共感」と「同情」は違う
よく「共感」と「同情」が混同されがちですが、この二つは全く違います。
- 同情:「かわいそうに」と、相手より少し上から(あるいは外から)相手の状況を憐れむ感情に近いかもしれません。
- 共感:相手の意見に「同意」するかしなくても、「相手の視点に立って、なぜそう感じるのかを想像し、その感情を理解しようとする」姿勢です。
大切なのは後者の「共感」です。相手の感情に寄り添い、「あなたは今、そう感じているんですね」と理解を示すことが、相手の安心感につながります!
自己開示と共感のサイクル
よく「自己開示」が大事って言いますが、あれも「共感」とセットだと思うんです。
一方が勇気を出して自分の弱みや本音を話した(自己開示)とき、もう一方がそれを「大変だったね」「そう感じたんだね」と受け止める(共感的理解)。
そうすると、開示した側は「この人は私を受け入れてくれる」と感じて信頼が深まり、さらに深い話ができるようになる。
そして、受け止めた側も「自分も話してみようかな」と自己開示を始める。
この「自己開示」と「共感的理解」のポジティブなサイクルこそが、関係性をグッと深めるエンジンになると思います。
もちろん、開示する相手や内容は選ぶ必要はあります。何を話しても否定してくるような相手に、無理に自己開示する必要は全くありません!
傾聴とアサーティブな伝え方

人間関係はコミュニケーションで成り立っていますが、多くの人が「うまく話すこと」「論破すること」ばかり気にしがちかもしれません。
でも、本当に大切なのは「聴くこと(傾聴)」です。
最重要スキル「傾聴」
「傾聴」とは、ただ耳で音を聞くことではありません。
相手の話を遮らずに最後まで真剣に聴き、相手が「何を伝えたいのか」「その背景にある感情は何か」を理解しようと努める姿勢です。
ただ黙って聞いているだけでは、相手は「本当に聞いてるのかな?」と不安になってしまいます。そこで効果的なのが「反射的傾聴」というテクニックです。
- オウム返し: 相手の言葉の最後や重要な単語を繰り返す。「〜で大変だったんです」→「そうか、大変だったんですね」
- 言い換え(パラフレーズ): 相手の話を要約したり、別の言葉で言い換える。「つまり、〜という点が一番気になっているんですね」
- 非言語的コミュニケーション: 言葉だけでなく、頷きやアイコンタクト、相手に体を向けるといった姿勢も「あなたの話を真剣に聴いています」という強力なメッセージになります。
コミュニケーションの核心は「聴く力」:
「傾聴」は、相手に「自分を否定しない人だ」という絶対的な安心感を与えます。人は、自分の話を真剣に聴いてくれる人に好意と信頼(基盤1)を抱くもの。うまく話そうとするより、まずは「最高の聴き手」を目指すのが良いかなと思います。
「伝える」技術のアサーティブネス
しっかり聴いた上で、今度は「自分の意見を伝える」ことも同じくらい重要です。特に「言いにくいこと」を伝える時です。
相手に嫌われたくなくて我慢したり、逆にイライラして攻撃的な言い方になったり…心当たり、ありませんか?
ここで役立つのが、「アサーティブな伝え方」です。
これは、自分の意見を我慢するのでもなく、相手を攻撃するのでもなく、自分も相手も尊重しながら率直に意見を伝える技術です。
「DESC法」というフレームワークが有名ですね。
DESC(デスク)法とは?:
自分の考えを4つのステップで整理して伝える手法です。
- D (Describe): 事実を描写する(評価や非難を入れず、客観的な事実だけを伝える)
- E (Express): 自分の感情や影響を表現する(「私」を主語にして、どう感じているかを伝える)
- S (Specify): 具体的な要求や提案をする(どうしてほしいのか、どう改善したいかを具体的に伝える)
- C (Consequences): ポジティブな結果を伝える(提案を受け入れた場合、どんな良い結果が待っているかを伝える)
このDESC法が特に役立つ場面の例を、「上司からの急な残業依頼」を元に見てみましょう。
DESC法の実践例
【状況:上司から急な(不可能な)残業を頼まれた】
非アサーティブ(受動的):「…はい、分かりました」(無理して引き受け、疲弊し、心身の健康を害する)
非アサーティブ(攻撃的):「無理に決まっるじゃないですか!いつも急すぎですよ!」(関係悪化)
アサーティブ(DESC法):
D: 「現在、私はA案件の資料を本日中の締め切りで作成しております」(事実を描写)
E: 「今このお仕事を引き受けると、どちらも中途半半端な品質になりそうで、私としては非常に心苦しいです」(自分の感情・影響)
S: 「そこでご相談なのですが、もし可能であれば、このお仕事は明日の朝一番に着手するのでは難しいでしょうか?」(具体的な提案・選択肢)
C: 「そのように調整いただければ、どちらの仕事も責任を持って質を担保できます」(ポジティブな結果)
このように、客観的な事実と「私」を主語にした感情、そして具体的な「提案」をセットで伝えることで、角を立てずに関係性を守りながら、自分の境界線(次の基盤)も守ることができます!
職場の人間関係と距離感

特に「職場」の人間関係は独特ですよね。
友達や家族と違って、ある意味「逃げ場のない」環境であり、集まっている第一の目的が「仲良くすること」ではなく、「仕事を円滑に進め、成果を出すこと」にあるからです。
厚生労働省の調査でも、職場のストレス要因として「対人関係」は上位に挙げられています。(出典:厚生労働省『令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)』)
この独特な環境で一番大切なのは、「適切な距離感」、つまり「深入りしない」ことです。
仲良くすることは素晴らしいですが、プライベートに踏み込みすぎたり、逆に踏み込まれすぎたりすると、ストレスの原因になります。
深入りしすぎると、社内の派閥争いに巻き込まれたり、個人的なトラブルに発展したり、あるいは相手への期待値が上がりすぎて「こんなに親しくしてるのに、仕事で助けてくれない」といった不満につながるリスクもあります。
職場で意識したい「ほどよい距離感」
意識してほしいのは、以下の点です。
職場で「やること」と「やらないこと」
DO(実行すべきこと):
- 「おはようございます」「お疲れ様です」「ありがとうございます」といった挨拶は、自分から笑顔できちんと行う。
- 仕事に必要な「報連相」は、相手が苦手な人でもしっかり行う。
- 特定の人とだけ固まらず、多くの人と「浅く広く」付き合い、孤立を避ける。
DON’T(避けるべきこと):
- 悪口や噂話には一切同調しないし、関わらない(トラブルの元です)。
- プライベートな話(特に家族、恋愛、お金、健康など)は自分からしすぎないし、相手にも聞きすぎない。
- 休日にまで無理して職場の人と接しようとしない(公私の区別は大事です)。
職場は「仲良しグループ」である必要はなくて、お互いをプロフェッショナルとして尊重し合い、機能的に協調できる関係がベストだと僕は思います。深入りしすぎて「期待」が大きくなると、裏切られたと感じた時のダメージも大きくなってしまいますからね。
友人関係を長続きさせるコツ

友人関係は、職場とはまた違って、より情緒的なつながりが中心ですよね。
「友人関係を長続きさせるコツ」も、基本はやっぱり尊重だと思います。
親しいからこそ、「ありがとう」や「ごめん」といった感謝と謝罪の言葉を、おろそかにしないこと。小さなことでも「この前は助かったよ、ありがとう」と言葉にするだけで、相手も「この友情を大切にしたい」と感じてくれるはずです。
そして、お互いの生活や価値観、時間を尊重すること。特に大人になると、結婚、出産、転職、介護など、ライフステージがそれぞれ変わってきます。
昔のように頻繁に会えなくなるのは、ある意味、自然なことなんです。
そこで「付き合いが悪くなった」と不満に思うのではなく、「今はそういう時期なんだな」と相手の状況を尊重し合えること。そして、「たまにしか会わなくても、会えば昔のように話せる」という形を認め合えるのが、本当の友人関係かもしれません。
共通の趣味があれば、それが関係を維持する潤滑油になることもあります。
家族関係と良好なコミュニケーション

家族は、一番近くて一番難しい人間関係かもしれません。
近すぎるからこそ、「言わなくてもわかるだろう」という甘えが出たり、遠慮がなくなって、つい感情的な言葉をぶつけてしまったり。
例えば、親が子供の帰りが遅い時に、「何時だと思ってるの!」と感情的に怒ってしまう。
でも、その言葉の裏には「事故にでもあったんじゃないか」「何かトラブルに巻き込まれたんじゃないか」という「心配」という本当の気持ちがありますよね。
しかし、子供にはその「心配」という本音は伝わらず、「非難された」「できていない部分ばかり見られている」という反発心として伝わり、結果として会話が途切れてしまう…なんてことは、よくある話だと思います。
「Youメッセージ」から「Iメッセージ」へ
この問題を解決するヒントが、「I(アイ)メッセージ」です。
- Youメッセージ: 「(あなたは)何時だと思ってるの!」(相手を主語にした非難)
- Iメッセージ: 「(私は)連絡がなくて、事故にでもあったんじゃないかと心配したよ」(自分を主語にした感情)
同じ内容でも、Iメッセージで伝えるだけで、相手は「非難された」ではなく「心配してくれている」と受け取りやすくなります。
家族関係で大切なのは、感情的にならずに相手の話を「傾聴」し、「オープンな質問」をすることだと思います。
「はい・いいえ」で終わる「宿題やったの?」(クローズド・クエスチョン)ではなく、「今日学校で何が一番楽しかった?」(オープン・クエスチョン)みたいに、相手が自分の思いを自由に話せる雰囲気を作ることが、信頼関係の第一歩になります。
悩み別:人間関係で大切なこと

ここまでは人間関係の「基盤」について話してきましたが、ここからは「じゃあ、具体的に悩んだ時はどうするの?」という、より実践的な悩み別の対処法について考えていきたいと思います。
「人間関係で大切なこと」は、悩みの状況によって、その優先順位やアプローチも変わってきますからね!
人間関係に疲れた時の考え方

「人間関係に疲れた」と感じるのは誰にでもありますよね。
なぜ疲れるのかというと、無意識に「相手に期待しすぎている」ということが多いのです。
「こうしてくれるはず」「普通はこうするべきだ」という自分の期待(自分のモノサシ)と、相手の実際の行動がズレた時に、私たちは「裏切られた」「分かってくれない」とストレスを感じるのです。
また、自己肯定感が低く、周囲の評価を気にしすぎるあまり「みんなに好かれよう」と無理をしてしまうことも、疲れの原因になります。
「自分の機嫌は自分でとる」と決める
対処法としては、まず「他人は他人、自分は自分」と割り切ることです。相手の価値観と自分の価値観は違って当然だと理解することです。
その上で、「相手に必要以上に期待しない」こと。「相手は変えられない」という前提に立ち、「きっとこうしてくれるだろう」という期待値を下げる。
これが心の平穏を保つ秘訣です。
心の余裕を生む「依存先の分散」:
「自分の機嫌は自分でとる」と決めて、仕事や特定のコミュニティ以外の時間(趣味、勉強、運動など)を充実させるのも、すごくオススメです。自分の世界が広がることで、一つの人間関係に固執しなくなり、「まあ、あそこでうまくいかなくても、私にはこっちがあるし」と、心の余裕が生まれます。これは「依存先を分散する」という考え方です。
合わない人への対処法

「どうしてあんなに合わないんだろう」という人は、どこに行っても必ずいますよね。学生時代も、職場でも、不思議と一人はいるものです。
まず大前提として、「合わない」のは「どちらかが悪い」わけではない、ということです。
単なる「相性」や「価値観」「物事の進め方」の違いである場合がほとんどです。
だから、「あの人を何とかしよう」とか「自分があの人に合わせなきゃ」と悩む必要はありません。
そういう人ともうまくやろうと「八方美人」になる必要はありません。合わない人への対処法は、「必要以上に関わらない」に尽きます。
もちろん、職場などであれば、挨拶や業務上の報連相は社会人として最低限行いますが、雑談などの業務に不要な会話は避ける。
相手の言動をいちいち重く受け止めず、適度に「受け流す(スルーする)」スキルも大切です。「あ、今、あの人はああいう考えで発言してるんだな(でも私は同意しないけど)」と、心の中で一歩引いて観察するような感覚です。
注意点:無理は禁物
合わない人と無理に仲良くしようとしたり、自分を理解させようとしたりするのは、膨大なエネルギーの無駄遣いになることが多いです。そのストレスで自分のメンタルがやられてしまっては本末転倒。「合わない人がいて当たり前」と割り切って、自分の心を守ることを最優先に考えるのが良いと思います。
人間関係をリセットしたい心理

疲れが限界に達すると、「もう全部リセットしたい」と思うこともありますよね。
連絡先を全部消したり、SNSのアカウントをいきなり削除したり…。
この「人間関係リセット症候群」とも言われる心理の背景には、以下のような特徴があります。
- 完璧主義の人: 失敗を嫌い、「あの人に失敗を見られた」といった些細なことを引きずり、関係をリセットしたくなる。
- 相談相手がいない人: 悩みを自分の中に溜め込みすぎて、パンクしてしまう。
- 周りの目を気にしすぎる人: 「どう思われているか」を気にしすぎ、表面上の付き合いで「本当の自分」を出せないため、気を遣うことに疲れ果てる。
リセットすれば一時的にスッキリしますが、根本的な問題解決にはなっていないことが多いのです。
なぜなら、問題は「環境」や「他者」にあるのではなく、「自分自身のコミュニケーションの取り方や考え方のクセ」(例えば、NOと言えない、完璧を求めすぎる、相談できない)にある場合が多いからです。
だから、環境を変えて(リセットして)転職や引っ越しをしても、同じ考え方のクセを持ったままでは、新しい環境でも結局、同じ問題に直面してしまう可能性があります。
本当の解決策は「リセット」ではなく、「自分自身をアップデート」することです!例えば、なぜ自分はリセットしたくなるのか、自分の価値観を書き出してみたり(自己理解)、信頼できる人に相談してみたり、前述のアサーティブネス(DESC法)を学んで「小さなNO」から言えるように練習してみることが大事だと思います!
※「人間関係リセット症候群」は医学的な正式な病名ではなく、
対人関係を急に切りたくなる心理傾向を指した一般的な呼び方です。
人間関係の修復と謝り方

一度こじれてしまった関係を修復したい時。これは本当に勇気がいることですよね。
ここで最も重要なのは「謝罪の質」です。口先だけの「ごめん」「すみません」は、かえって関係を悪化させます。
やってはいけないのは、「弁解」や「正当化」です。
- 悪い例(弁解): 「電車が遅れました、申し訳ありません」
- 良い例(説明): 「申し訳ありません。電車が遅れました」
この違い、わかりますか?「申し訳ありません」という謝罪を先に言うことで、「自分の言い分(電車が遅れた)」よりも「相手の感情(待たせて不快にさせた)」を優先するという姿勢が伝わりますよね。
親しい関係ほど「行動」が求められる
特にカップルや家族など、親しい関係性においては、口だけの「ごめん」という「安易な謝罪」は逆効果である場合が多いです。
怒っている相手が本当に求めているのは、その場の謝罪の言葉ではなく、「自分のことを丁寧に扱ってほしい」という態度の改善や、時間的な投資(例:一緒に家事をする、話を聞く時間を作るなど)です。
安易な謝罪は、わだかまりを残したままになり、真の仲直りにはなりません。
離れるべき人と有害な人間関係

すべての関係が修復可能とは限りませんし、修復すべきとも限りません。
中には、自分の心と未来を守るために、勇気を持って「離れるべき人」もいます。
これは「有害な人間関係(トキシック・リレーションシップ)」とも呼ばれますね。
「離れる」ことになんとなく罪悪感を感じるかもしれませんが、これは「冷たい」行為ではなく、「自分を守るための重要な自己防衛手段」です。
どのような場合に離れるべきかを整理してみました。
「離れるべき人」の見分け方チェックリスト:
- 相手から大切にされていると思えない、リスペクトを感じない。
- 一緒にいると、エネルギーを奪われる、いつも疲弊する。
- あなたの「NO」を尊重せず、あなたの領域にずかずかと入ってくる。
- 常にあなたを悪者に仕立て上げようとしたり、罪悪感を植え付けようとする。
- あなたの他の友人関係や成功に嫉妬したり、妨害しようとする。
- 同情を買うために平気で嘘をつく。
- 自分の家族や本当に大切な人に、自信を持って紹介できるか自問した時に「迷う」。
有害な関係から離れることで、相手に振り回されることがなくなり、心に大きな余裕が生まれます。そして、不要な縁を手放すことで空いた心のスペースに、新しい健全な縁や可能性が入り込みやすくなります!
人間関係の判断は慎重に。危険を感じたら専門家へ
人との関係を断つかどうかの判断は、非常にデリケートな問題です。感情的になっている時はいったん距離を置き、冷静になってから判断することが大切です。
ただし、もし相手の言動がエスカレートし、ストーカー行為、モラハラ、パワハラ、DV(身体的・精神的暴力)など、あなたの心身や財産に具体的な危険が及んでいる場合は、決して一人で抱え込まないでください。
それは「人間関係の悩み」ではなく「事件」です。迷わず警察(緊急時は110番、相談は#9110)や、弁護士、各種ハラスメントの相談窓口など、法的な専門機関に速やかに相談してください。
まとめ|人間関係で大切なこととは?
ここまで、人間関係の5つの基盤や、悩み別の対処法についてお話ししてきました。最後に、この記事を通して一番伝えたいことがあります。
それは、人間関係で大切なことの多くは、生まれつきの「性格」や「相性」といった曖昧なものではなく、「スキル」であるということです。
もちろん、もともと持っている性格や相性もゼロではありません。
しかし、「傾聴」や「共感」の姿勢、そして「アサーティブネス(DESC法)」といった「伝え方」は、すべて後からいくらでも学習し、日々のトレーニングで上達させることができる「技術」なんです。
「自分は口下手だから」「コミュ障だから」と諦めてしまうのは、すごくもったいないことだと私は思います。
「人間関係がうまくいかない」と今悩んでいる人は、性格が悪いのではなく、ただ「そのスキル(技術)を知らないだけ」かもしれません。
だから、焦らずに一つひとつ実践し、「今日はDESC法で『S(提案)』まで言えた」とか、「相手の話を遮らずに最後まで聴けた」といった、「小さな成功体験」を積み重ねていくことが大切だと思います。
この記事で紹介したことが、あなたの「人間関係で大切なこと」を見つけるヒントになり、あなたが自信を持って充実した毎日を送るための一助となれば、これほどうれしいことはありません。
参考リンク:
・World Health Organization(2025)
Mental health and social connection. Report by the Director-General (EB156/8)
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_8-en.pdf
・World Health Organization(2025)
Mental health
https://www.who.int/health-topics/mental-health
・Holt-Lunstad Jほか(2010)
Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
・Pietromonaco PR, Collins NL(2017)
Interpersonal mechanisms linking close relationships to health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5598782/
・厚生労働省(2023)
令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r04-46-50.html
・厚生労働省(2025)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関 するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
・内閣府男女共同参画局(2016)
配偶者からの暴力被害者支援情報
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html
・内閣府男女共同参画局(2016)
DV相談について(DV相談ナビ・DV相談プラス)
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html
・政府広報オンライン
警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ
https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html